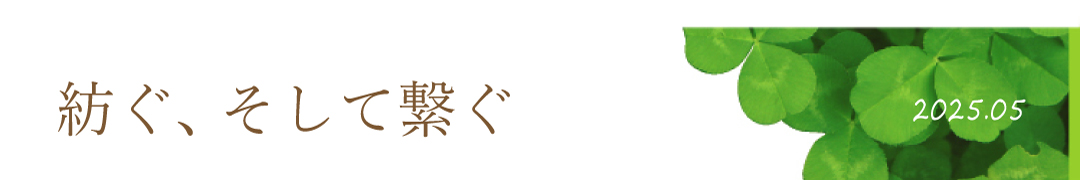 先日、お釈迦さまのお誕生日をお祝いする花まつりが行なわれました。
先日、お釈迦さまのお誕生日をお祝いする花まつりが行なわれました。
長年、神應院ではお寺の婦人会とか、青年部、日曜学校関係者が中心となってご縁のある方の中で行なわれてきました。
けれども境内で行なわれているバザーを気にしながら門前を通り過ぎていく人を見る度に、このままの形で良いのだろうかと思い続けてもいました。
時代が変わり、コロナ流行という大きな出来事もあり、お寺の状況も変わって来たのをみて、今年は実験的にマルシェを取り入れ、一部のお参りだけ申込み制にし、自由に誰でも参加できる形に変えてみることにしたのです。
しかし、この形にすると、大半の人は、買い物や食べ物ブースを目当てにマルシェだけ参加される方が多いだろうという心配がありました。
正直、お寺側とすれば一部のお誕生佛をお祀りし、甘茶を注いでお祝いするお参りの時間こそ参列して頂きたいというのが本音です。
でも、それは望めないだろうと考えていました。
ところが、告知を始めたところ、以外にもたくさんの方々が一部の法要から参加して下さいました。
しかも家族で、子ども連れでという方も多く、後日あった方からは、『とても感動した』と感想を頂いたほどでした。
新しい試みに踏み出すというのは勇気がいるものです。
時代と共に変わっていかなければいけないとよく言いますが、何を変えて、何を残していくのか、その判断がとても難しい。
最近は「らしい」ということは禁句のようになってしまいました。『男らしい』『女らしい』
でもいつも思うのは神應院には神應院らしい空気があり、変化はしていくけれど、それだけは失いたくないと思っています。
今、世界のあちらこちらで紛争が起こり、戦火の中で暮らす人も多い。
一方、平和で豊かに見える中で、人との関係性が薄れ孤独感に苛まれ、追い詰められていく人も多い。
そんな社会の中で、お寺はどうあるべきかとお寺の社会性を考えるのです。
人との繋がりが薄くなり、家族という関係性も希薄になって、そうした流れが人を孤独にしていくように思います。
お寺というと「死」ばかりがイメージされますが、本来、お寺は生きていくことを考える場なのです。
「死」を通して「生」を考える。
亡くなった人を偲ぶということも、『偲』という字が示すように亡くなった後もその人のことを思い続けていく。
亡くなったから自分とその人をつなぐ糸が切れるわけではなく、亡くなっても尚、繋がり続けているというのが『偲ぶ』ということだと思うのです。
思うことにより、逆に思われている、見守られていることも感じながら人は生きているのです。
お寺は、そうした関係性を繋ぎ合わせていく場ではないかと思います。
生きている人、亡くなってしまった人、その総てを繋ぎ合わせていく場所。
様々な人が世代や性別を超えて交流し、縁の糸を紡いでいく場。
その糸に支えられて、人は孤独な気持ちが癒やされ、励まされ、肩の力が抜けて前に進んでいこうとする気持ちになってくるのだと思います。
お寺は何をすべきか。
そうした場を整え、提供していくことが大きな役目なのではないかと考えています。
