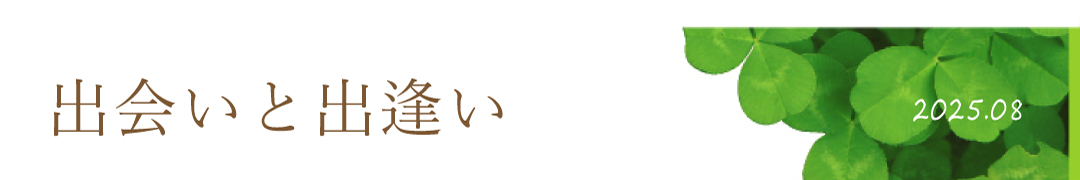
最近しみじみと人との繋がりを考える。
お寺の婦人会は発足から32年、日曜学校は70年を越し、そのメンバーは、お寺の様々な行事で裏方を勤めて大きく支えて下さっている。
婦人会の始まりは、ほんの小さなつぶやきだった。
日曜学校の子どもたちと、越智さんという宮島のしゃもじ職人の方の工房を訪ねた折、
その話に私と子どもたちは心が揺り動かされた。
その感動が子どもたちからお母さん達につながり、「私たちも是非」ということで再び訪問。
その帰り道のこと。
「花まつりの時だけでなく、こうしてみんなが集まる会が出来ないものだろうか」
と、ぼそりと言われた。
それが32年間の始まりだった。
もしあの時、子どもたちが越智さんを訪ねたことを楽しそうに話さなかったら・・・。
もし、あの時、あの発言がなかったら・・・・。
もし、あの遠足で越知さんを訪ねていなかったら・・・。
いろんなものが重なり合って、「今」という瞬間に繋がっている。
縁というものは本当に不思議なもので、今、婦人会で中心になって支えてくれている何人かのメンバーの中に私の幼馴染みと年上の旧い友人がいる。
幼馴染みは赤ん坊の時からの知り合いで、旧い友人は私が高校生時代に知り合った。
しばらく縁が遠のいていたけれど、何度か街中でバッタリと会うことが続き、彼女の言葉によると「これは運命だなと思って」と以来、公私ともに支えてくれている。
考えてみると、こうして無数の人々との縁に支えられてきた。
先日、毎年恒例のお寺のボランティア行事であるアジア祭りが無事に終わった。
一部のボランティア講座の後、二部は、柳家さん喬師匠の落語という構成になっている。
のっけに、さん喬師匠が「神應院に伺うようになって今年で20年になる」と話された。
もうそんなにも月日が経ったのかと思いながら、この縁を繋いでくれた友人のことを思った。
柳家さん喬師匠に是非お越し頂きたいと考えたとき、その縁を繋いでもらうルートのひとつに彼女がいた。
けれども8年のご無沙汰だったので、そんな勝手なお願いをするのはさすがに気が引けた。
ところが、突然、彼女から「元気?」と電話が掛かり、しかも会いに来るというのだ。
そんな奇跡的なことがあって、さん喬師匠との縁は繋がった。
本当に縁とは不思議なものである。
「逢」という漢字が、私は好きだ。
同じ「あう」でも「会う」とは違う、この逢うの二つの点が好きだ。
全く別の二つの点が偶然なのか、必然なのか分からないけれど、引かれるように出会って縁という糸で人生を紡いでいく。
この字は、その神秘的な出逢いの瞬間を表しているような気がするのだ。
そのことを同じように感じている人がいた。
詩人の若松英輔氏が『言葉の羅針盤』の中で書いている。
出会いは作るものだ、という人もいる。「会う」ということはそうかもしれない。
しかし、「逢う」時機がいつ訪れるかは、人の自由にはならないのではないだろうか。
会って、顔を見たり、言葉を交わしたりするのは難しくない。
しかし、心と心がふれ合うような出来事を「逢う」というのだとすれば、それを人が作り出すことはできない。
この箇所を読んだときに、私は本を掴んで震えた。
この文章には、まだ先があり、詩人はもっと思索を深めていくのだけれども出逢いということ、縁ということの深さに気づかされたような気がした。
私たちは、日々たくさんの人と出会う。その出会いが出逢いに熟成されていくまでの時間が日常という時間なのだと思う。
その平凡とも思える日常の時間を大事に、戴き物のように丁寧に受け取りながら過ごしている間に「出会い」は「出逢い」に熟成されて、人生の中で芳醇な香りを醸し出し始める。
日々の暮らし、何気なく思える毎日の一歩が、その始まりに繋がっていく。
