10月神應院佛教講話会のご報告
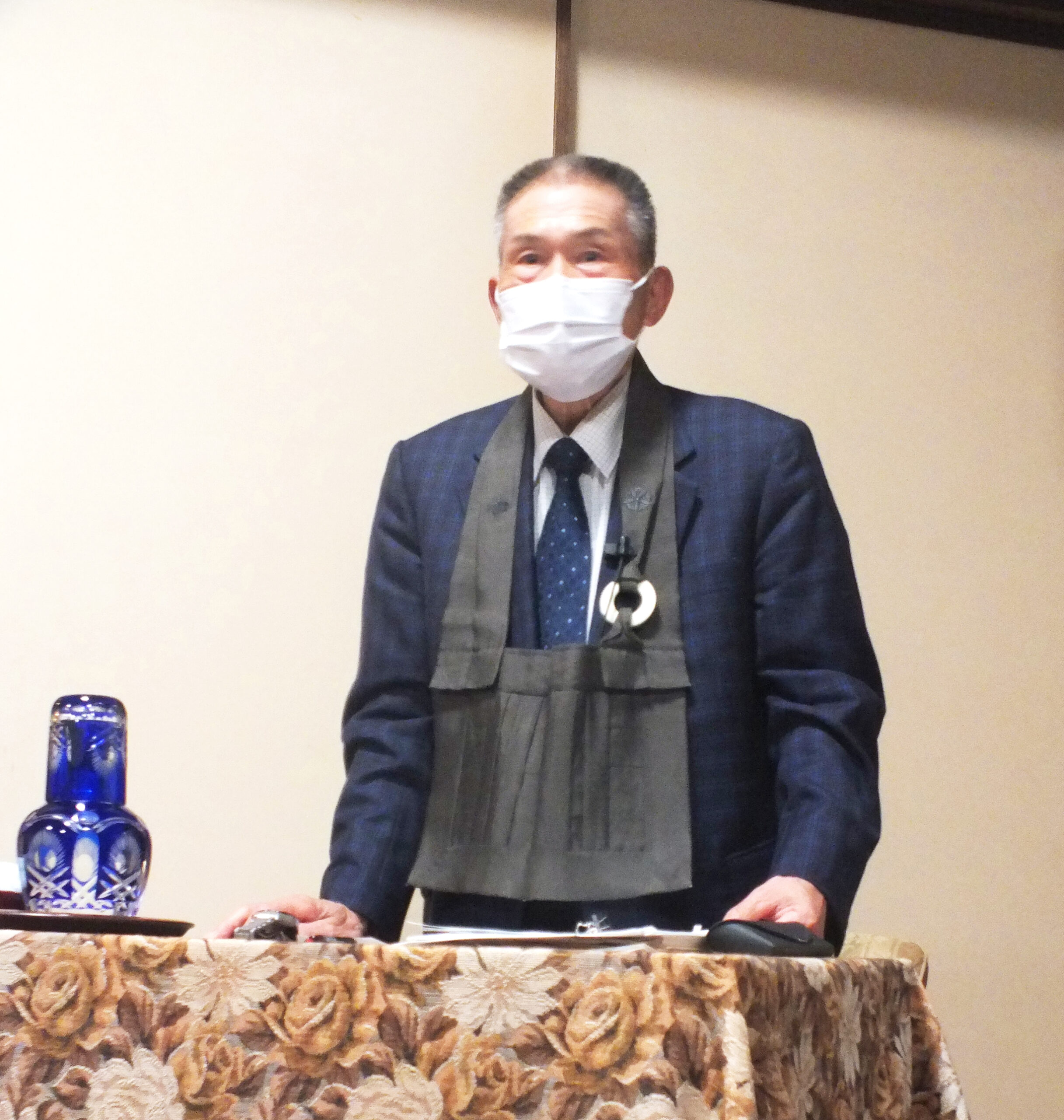
【講師】 常仙寺住職・育英短期大学名誉教授 佐藤達全先生
BUDDHA 生命の本当のすがたに気付いた人という意味。
「生まれる」は、受け身
気が付けば、生まれていた。
生まれているのだけれど、自分の思い通りにはいかない。
生老病死という苦が、生きていく上で常について回る。
しかし それを見据えながら諸法無我(しょほうむが)という教えを生かして、「おかげさま」「ありがとう」という感謝の心を忘れない生活を送りながら、自分の都合の良いことばかりではないことに気付くことが大事。
そして、その苦が固定したものではなく受け取り方次第で変化していくものでもあることに気付くこと。
― 諸行無常 諸法無我 ―
「いのち」は、私ひとりで完結しているわけではない。
多くの人や、動植物の力によって助けられ、生かされている
人は他の人の力を借りて、生きているのだということを認識する。
「縁起」とは、関わり。私という個人は、他のいのちに依って助けられて生きている。他との関係性の中で成立している私の「いのち」ではあるにも拘わらず 、その重要なポイントを今、人々は忘れてしまっているのではないか。
「頂きます」という言葉は、ただ食べることだけではない。
植物、動物のいのち、自分に届くまでの間、関わって下さった多くの方への感謝、総てに対し「頂きます」と手を合わせる。
自分は正にひとりでは生きていかれない。多くの人に助けられ、他のいのちを頂いて自分のいのちを生かしている。その事実にしっかり目を向けること。
「勿体ない(もったいない)」という日本の古くから伝わる言葉をグリーンベルト運動を広めたケニアのワンガリー・マータイさんが注目し、その精神性を深く理解し世界に広めてくれた。当の日本人が忘れていた「もったいない」という精神を再び蘇らせてくれたような思いだった。
現代、豊かになったという。物は溢れ、食べるものは簡単に手間暇掛けなくても、即、食べられる。
でもスピードが速くなった分、「頂きます」といういのちに向き合う心持ちは軽んじられてきた。
もったいないという精神をもう一度取り戻していくことが「いのちを大事にする」ということに繋がっていき、それは他との関係性を重んじていくという「繋がり」という縁を大事にしていくことに結びついていく。
「ダイヤはダイヤで磨く」という言葉がある。その意味は、地球上に存在する最も固いダイヤという鉱物を磨くためには、ダイヤの粉を用いるしか方法がないということである。それと同様に、人間の心は人間と触れあうことによってしか育てられないのである。言いかえると、〈いのち〉を育てるためには〈いのち〉と〈いのち〉の触れあう場がなくてはならないはずである。


